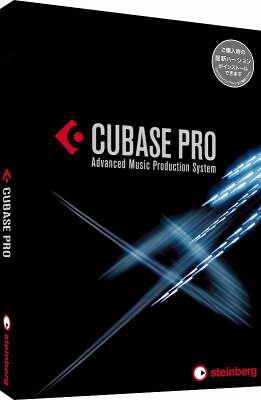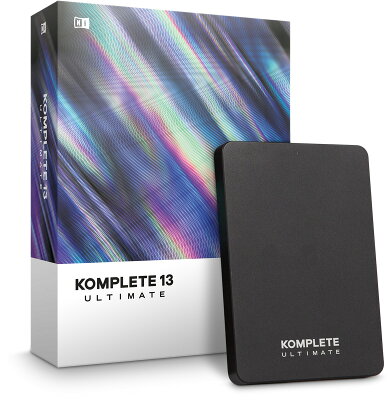楽器を練習するなら、録音して後から聞けると上達が早い。
よく言われる話だと思います。かつて「録音をする」というのは特別で大変なことでした。
まず、そもそもギターを“まともな”音で録ること自体のハードルが高かったのです。
ミックスの話に入る前に、まずは簡単に、90年代~の録音環境の違いからいきます。
「宅録」。自宅で録音するという意味ですが、そういう言葉が一般的にも知られるようになったのが90年代ごろでしょうか。
レコーディング、それもプロが出す音源のレコーディングはレコーディングスタジオで行われるのが当然だった時代です。今でも個人的に覚えているのが、the brilliant greenのメジャーデビュー曲“There will be love there -愛のある場所-「宅録で作られた」と音楽誌に載っていて、びっくりしました。前にもどっかで書きましたけど。
the brilliant green - There will be love there -愛のある場所- (live)
もちろんCD化にあたってプロのエンジニアの手は入っているとは思いますが、元のトラックは宅録で録られたもの、ということだったと思います。
なお、当時私は宅録ってのは自宅で録音することなのは知っていてもどうやるかとか知りませんでしたが。
まぁ、まだ自分のギターも持っていない時代の話です。そんな時代の「宅録」がどのようなものだったのかというと、「MTR」という機材を使いました。

MTRとはマルチトラックレコーダーということ。一般的な「録音」がカセットテープやMDだった時代です。カセットテープやMDの録音ってステレオ2mixなんですね、普通。つまりトラック数はステレオトラックが1つのみ。
それに対して、複数のパートの音を重ねたマルチトラックを録音できるから、マルチトラックレコーダーなわけです。
MTRは過去の遺物ではなく今でも販売されています。見ればわかりますがミキサー卓みたいなデザインの機材です。
というか、複数のトラックを録音し、音量やパン、エフェクトなどをかけてミックスダウンができるわけですから、当然ミキサーとしての機能も備わっていますね。
そんなMTRを使った「宅録」がどんなものかというと、まずMTRを持っている人の家に集まったり、MTRをスタジオに持ち込みます。
そしたら、各楽器やヴォーカルのマイクをMTRにつないで、音を出してレコーディングを行います。もちろんいろいろなスタイル、方法での録音が行われたことだと思いますが、基本的にはこんな感じでした。
このあたりは、2000年代に入っても大きな変化はあまりありませんでしたが、PODをはじめとするマルチエフェクターのアンプシミュレータも普及し始め、徐々に「普通の自宅でも十分な音が録れる」ことが広まっていきます。
バンドの録音形態はまだ大きく変わっていませんでしたが、2000年代には後のレコーディングに影響する動きがありました。
1つが各家庭に光回線が普及し始め、いわゆる“ブロードバンド”接続が当たり前になりつつあったことです。
それに伴う高速データ通信が可能となると一気に加速したのが“DTM”、デスクトップミュージックの世界です。
それまで.midという「MIDIファイル」を読み込み、PCに内蔵されたり専用に購入した音源モジュールから音を出して再生していたデスクトップ音楽が、オーディオデータに置き換わります。つまり、「造り手が音まですべてを作る」ことができるようになりました。それまでは演奏情報のみをやりとりし、音はそれぞれの環境にある音源モジュール(要はシンセ)が出していたのが、一般的に販売される音源と同様のデータを作って送ることができるようになります。
ちなみに、今でも「PCで音楽を作るなら」まずはDomino(有名な無料MIDIシーケンサー)から始めましょうと書かれていることがあります。が、今ではもう少し古いのかもしれませんね。どうしてもMIDIシーケンサーという形を使いたい人向けという感じがします。
そう、つまりこの情報スピードが速くなったことにより、MIDIシーケンサーに演奏情報を打ち込むDTMと、生のオーディオデータを扱うのが前提の「宅録」の隙間が埋まったのです。
2000年代の中頃、「あなたのパソコンがMTRに」という広告をよく見かけました。製品名までは覚えていませんでしたが、それはDAWの広告でした。
それはシーケンサーであり、レコーディングソフトであり、シンセサイザーであり、エフェクターです。ProTools、CuBase、Logic、Studio One、Garageband……そのスタイルは様々ながら、多くのDAWがあり、そこからは様々な音が生み出されています。
さて、2007年8月31日、のちの音楽業界を動かすソフトウェアが発売されます。
「初音ミク」。ヤマハの開発したVOCALOID2エンジンに対応する日本語対応の発声ライブラリであり、ソフトウェアシンセサイザーの一種です。現役の声優の声をサンプル、合成して作られた「声」であること、そしてパッケージにその声からイメージされたキャラクターを描いたこと。それらの相乗効果、そしてニコニコ動画全盛期が重なったことにより「ボカロ」というジャンルが生まれ、特に2007~2012年頃にかけては全盛期と呼べるほどの盛り上がりを記録しました。
このボカロというジャンル、単にボーカロイドがヴォーカルを取っていればいいだけなので音楽的には様々なジャンルが含まれます。そして、曲をきちんと完成させて公開するもののため、ボカロPと呼ばれるコンポーザー、特に長く活動している人ならゼロから楽曲を完成させることができる人が多くなります。今はかなり分業体制が確立して、曲の構成、打ち込み、ボカロ調声までできればミックスを依頼したりすることも多くありますね。
依頼をするにしても自分でやるにしても、この時点で楽曲を自分だけで、それもスタジオに入らずにリリースできるレベルに完成させることができるようになる。これは90年代の宅録の時代からは考えられないような進化です。
楽曲もライブをしてCDで出す、バンドの基本的な方法だけでなく、ウェブストリーミングでの公開や、ボカロ曲としてMVを付けての公開など、様々な方法ができるようになっていますね。
で、いわゆる作曲能力が高く、また人気も高いボカロPがメインストリームに進出しているのが最近の音楽業界ではよく見られます。ボカロP、ハチとして活躍した米津玄師はもちろん、supercell / EGOISTのryo、PENGUIN RESEARCHの堀江晶太、YOASOBIのAyase、うっせぇわの作詞作曲を手掛けたsyudouなどはもちろん、ほかにも多数アーティストがボカロを経験していますし、さらに裏方として音楽制作に関わっている人も含めればかなりの人になります。
DTMからボカロ、そしてメインストリームへ。この流れはそのままインターネットをとりまく環境の動きと連動しているのがよくわかります。
と、大体かつての宅録から今の音楽業界への流れまで書いてきました。
なぜこれを書いたのかというと、「これから」を考えるためです。
ギタリストは楽譜が読めなくても弾ければそれで良い、という時代は終わりつつあるのでは、ということです。
もちろん楽しくギターを弾いたり、“演奏してみた”動画を作ったり、というのはとても良いと思います。また、明らかに頭が抜けたようなスキルや感性があれば、ただギターを弾くだけで十分な活動ができることでしょう。
ですが、「これから」音楽をやっていくなら、かつてのようにミックスはそのエンジニアに任せればいい、という時代ではなくなっているのでは、と思います。
今、アーティストのレコーディングでは「メンバーが集まって順に弾いていく」ようなスタイルは少なくなっています。それぞれがトラックに音を録り、それをデータで送信してそこに自分のパートを入れていく。もちろんスタジオで行うレコーディングもあれば自宅でやることもあると思いますが、いずれにしてもどこかにみんなで集まって、というやり方は、特に今、プロのレコーディングではほとんど行われていません。
かつて、本格的なミックスはスタジオでないとできませんでした。自宅でできるような人はとんでもない額の機材、そして部屋が必要だったからです。
もちろん今でもプロの音源になるミックスはそういったミックスのプロが手掛けています。自宅でそこまでできる必要は、まだないかもしれません。
ですが、少なくとも楽曲の録音データからパラミックスをして自分なりの音源にすることができる…そこまでできるのが「当たり前」になる時代はもう来ているのでは、と思います。それはプロのクオリティである必要はありません。当然、その道のプロに適わないことは多数あると思います。でも全部任せとけば良い、という時代でもなくなっていますよね、ということです。

ちなみに、パラミックスというのは、楽曲を構成するすべてのデータのバランスを取って1つの曲に仕上げる作業のことです。最後にマスタリングの工程がありますが、マスタリングはいわゆる音量調整のことを指します。厳密にはその手前までがパラミックスですね。
「ミックスは難しい」と思われることがあります。
今、「ミックス師」 と呼ばれる人たちがいます。ボカロ系はもちろんですが歌ってみただったり、ボカロ以外のオリジナル楽曲でもなんでも、ミックスして作品に仕上げる人のことです。それをSNS上で受付け、有償で行う、いわば「フリーのサウンドエンジニア」という感じですね。
そういう仕事が成り立つほど、たしかにミックスは奥深いです。これはどんなものでもそうだと思いますが、「クオリティの高いものに仕上げる」のは難しいというか、今日はじめてすぐにできるものではないのは間違いないでしょう。
そのクオリティを求めるためにプロに依頼する、というのは何もおかしいことではありません。
一方、自分の曲を自分で仕上げてみる、というのもまた自然なことではないでしょうか。
自分で一度形にしてみる。それはできる範囲で良いのです。できる範囲ででも形にすると、自分の作っている曲の全体から細部までがよりクリアに見えてきます。
この部分はこうだったのか、ということが見えると、曲を作る上でもさらに良い形、自分のいきたい形へと近づくことができるようになります。

ミックスは機材やソフトを揃えるのが大変?
「かつて」はそうだったかもしれません。もちろん、たしかに、有償のソフトを使えば、より早い時間でより高いクオリティの結果になることもあります。
ですがある程度のクオリティまでなら、別にお金をかけなくてもいけます。
iPhoneにGaragebandというアプリがあります。いろいろな制約はたしかにあるんですが、これだけでも楽曲を完成させることはできますし、iPhoneだけでボカロを作って投稿している人もいます。
WindowsのPCを持っていれば、完全なフル機能を持ったDAW、Cakewalk by BandLabが無料で、一切の成約なく使えます。
実際、私もCakewalk by BandLabとボカロ、ギター・オーディオインターフェースだけで楽曲を完成させました。それは自分なりの形になり、動画としても投稿しています。
この記事のシリーズでは最初に音を出すところから楽曲の打ち込み、ギターの録音、ボカロ調声、ミックス、マスタリングまで記事にしているので、よかったら見てもらえればと思います。
まずはこんな感じで、実際に楽曲を完成させてみるのが良いと思います。
いや、でも面倒だし。そう思うのも無理はありません。私もミックスって何?って頃はこんな楽しいものだなんて思ってませんでしたから。
なぜミックスまでできるようになると良いのか、ということをいくつか書いてみます。
・音作りがうまくなる。
楽曲全体の流れ、バランス、今鳴っているパートを考え、欲しい音を作ることは重要です。自分だけが気持ち良い音を作っても、それも楽しいですが、それだけでは楽曲は仕上がりません。
ミックスをきちんと体験して実践できるようになると、どういう場面でどういう音になるのかがより分かって来て音の作り方も変わってくる、ということがあります。
・新しい音へのアイディアが出てくる。
音はフレーズに繋がります。音が出来ると、そこから新しいフレーズが生まれ、フレーズを作ると、それに合った音を作りたくなります。これはミックスしていなくてもそうなんですけど、例えばギタリストならギターのフレーズをいろいろ覚えるだけではなく、曲全体での動きを考えてフレーズを作るようになると、そこから新しいアイディアが出てくることがあります。
・出来上がりを想像できるようになる。
これが一番大きいですね。今作っている曲があって、「こういう風にしたらこうなるんじゃないか」という方向がすごくわかりやすくなります。
例えば、ある場面であるパートを目立たせたいとき、そのパートの音を足すべきか引くべきか、とか。もちろんミックスしなくても出来る人もいますが、全体のミックスをしているとそういう考え方がより出やすくなる、ということはあるのではないでしょうか。
これまでも書いていますが、「自分でプロレベルの完成形が作れるようになろう」ということではないんです。
曲を作るなら、今のプレイヤーなら何らかのDAWを使うのが一般的になっています。そのDAWの機能をより深く使って、自分で自分なりのミックスをしてみよう、というのがこの記事の趣旨です。
実際にリリースするものはプロに依頼しようが関係ありません。自分なりのミックスを形にできるようになってみませんか、ということです。
仮にバンドのメンバーが4人いたとして、4人がそれぞれ同じパラデータ(録音したトラック)でミックスをすると、それぞれ違った結果になると思います。
それを聞き比べれば、そこからさらに新しいアイディアが生まれてきたりしますし、「このパートのメンバーはこういう風にやっていたんだ」ということがより深く理解することもできるようになります。
これって、すごく重要なことだと思うんですよね。
ミックスに必要な機材。とりあえずこの時点で、録音機材等はあって、トラックの形になっているものとします。(オーディオインターフェイスやらマイクやらいろいろ…それぞれが必要なモノは持っているとします。)
録音したトラックを並べているのですから、DAWも何らかの形で使っていることでしょう。
もし、より「自由度の高い」ミックスをしたいと思うなら、DAWは最上位モデルを使いましょう。使い慣れたもので良いです。それが機能制限版なら、最上位モデルにアップデートはした方が良いかとは思います。
Windows機用になってしまいますが、前述の無料DAW、Cakewalk by BandLabを使うのも手です。これは最上位のDAWの機能を持っていながら完全無料です。これは本当に革命です。
あとは…できればモニタースピーカーを。最低1万円くらい、できれば2~3万円台のものがあると良いです。音を録るのはヘッドフォンでOKですが、ミックスはスピーカーでやらないとバランスがうまく取りにくくなります。
そんな予算はない、とかPC持ってないという方でも、Garagebandでもある程度ミックスはできます。スピーカーはあった方が絶対良いんですが、ヘッドフォンでもできなくはないです。
できる範囲で自分なりの形にまずは仕上げる。まずはその1歩を踏み出してみましょう。
なお、ヘッドフォンでのミックスの注意です。MDR-CD900STでのミックスは避けましょう。モニターヘッドフォンということで間違いがちなんですが、あれはレコーディングモニターであってスタジオモニター用ではありません。同じく900STと並べられて比較される「モニターヘッドフォン」はレコーディングモニターであることが多いので注意です。ミックスという視点でいえば、900STより普段リスニング用に使っているヘッドフォンの方がまだ良いと思います。
toy-love.hatenablog.com
ここからは、よりハイクオリティなミックスをしたい、という人向けです。DAW、それが最上位モデルであっても、ミックスをより高いクオリティで仕上げたい、となるとどうしても追加のプラグインの力が欲しくなって来ます。まずは手軽に、よりクオリティを高められるプラグインを載せてみます。
Waves Gold
あと価格も含めて考えれば、これ以上に手軽に使えるミキシングのプラグインはそうそうありません。
……というか、そうですね。いくつか書こうかと思ったんですが、GOLDが圧倒的にお手頃すぎたので、並べるものが全然ないです。とにかく予算はかけたくないけど、Webに作品としてアップできるものを作りたい、と思うならGOLDはあった方が良いかもしれません。
他だと、iZotope Elements Suiteあたりは価格帯的に近いんですが……
 iZotope Tonal Balance Bundle Crossgrade from Waves Gold/Horizon
iZotope Tonal Balance Bundle Crossgrade from Waves Gold/Horizon
これだけで終わるのもなんなので、自分が今、「曲作りからミックスまで」全部含めてあまりに有用で手放せないなと思っているものを紹介したいと思います。先に言いますが、コストパフォーマンスには全く優れていません。
ここから紹介するものを使って作ったボカロがあるので、良かったら聴いてもらえたら嬉しいです。
Kemper Profiler
リアルなアンプで出した音がそのままラインで送れることの楽さたるや。
もちろんGE200
FX Pansion BFD3
ただ、BFDの利点は、音がリアルだから素晴らしいってのももちろんあります(最初はそれで買ったし)が、音がリアルゆえに、Web上にある「ドラムを録音してミックスなどに使うTips」が自然にハマるってのがすごく大きかったです。ドラム音源だと生ドラムのTipsが役に立たないこともあるんですが(BFDでももちろんあります)、それがだいぶ近い形で反映されるのはさすがでした。
IK Multimedia Total Studio 2 MAX
Native Instruments KOMPLETE Ultimate
ピアノとかストリングスも、本格的にオーケストラやるならまた違ってきますが、ロック系に添えるものとしては非常に高いクオリティの音源で、手放せないです。ちなみにうちのKOMPLETEは12です。
 Waves Mercury
Waves Mercury
「100まんえん」の価格は気にしないでください。なぜならWavesは様々なセールやアップグレードでのプライスダウンがあるからです。最初から全部そろえたいならこれでもいいんですが、うまいこと買えばかなり安くなります。私の場合は最初にDiamond
GOLDで十分とか言ってなかったっけ?って思うじゃないですか。とりあえずちゃんとしたミックスにするならGOLDで十分なんです。ただ、これはやっていけば分かるんですけど、GOLDでは曲の「ここの部分をこうしたい」まではできるんです。でも、「ここの部分“だけを”こうしたい」ってなってくると、Mercuryにしか入っていないプラグインの出番がより多くなるんです。
ただ、最初はそこまで求めなくていいです。そこまで求めたいなら、ちまちま上げていくよりMercuryにしちゃった方が楽かもしれません。
iZotope Ozone Advanced / iZotope Neutron Advanced
/ iZotope Neutron Advanced
Neural DSP Darkglass Ultra

ベース音源にかけるプラグインとして、Amplitubeがクラシックベース用なら、モダンベースにはこのプラグインを使います。動作も軽くて音も良いです。
A.O.M Invisible Limiter
aom-factory.jp
IKのStealth Limiterと並んで使うリミッター。最後の音圧調整に。音のバランスをほとんど変えずに音圧だけを上げるリミッターとして有名なモデルですね。Stealth Limiterはちょっと音がファットに、Invisible Limiterはちょっと音に透明感が出る感じ。どっちもほとんど変わりませんが、楽曲の方向性に合わせてどっちを使うかって感じです。
Pioneer RM-05

あと忘れてはいけないのがモニタースピーカー。個人的な趣味というか好みで「同軸」にこだわりたかったので、こちらを使っています。あんまりモニタースピーカーとしては定番ではない機種ですが、素直な音で聴き疲れもほとんどなくてとても良いモデルです。
同軸(ウーファーとツイーターが同じ軸上にある)ことから、左右の定位が見えるように聞こえます。自分の曲調整で欠かせないのはもちろん、いろんな曲を実際に聴いた時のバランスがはっきり見えたりして、とても良いです。
こんな感じでしょうか。
エフェクターとかと同じでプラグインにも沼ってのがありまして…新しいのが出たり、こっちの方が良いよってのがあるとどんどん使いたくなってきたりするんですが、実は何よりも「元の曲」と「アレンジ」が楽曲では重要なんですね。ここに挙げたバンドルウェアとかは、そりゃこんだけあれば何でも出来るでしょレベルのものなんですけど、私の場合はここまで揃えたらなんかもう十分って感じになりました。
UADとかも試してみたい気持ちはありますし、なんかたまにプラグインの記事とか見るとすごい良さそう…と思うものも多くあるんですけど…今のところ、上に書いたとおりこれらの中で手放せないと思うプラグインや音源は見つけましたが、まだ正直全て使いこなせてないなと思うので、しばらくはこのままの環境でいろいろまた作ってみようかなと思っています。
ということで、最後はなんか今のうちの環境紹介になっちゃいましたが…今ならやはり、ある程度ミックスというか、曲全体を自分でまとめられるようになるとまた新しい世界が見えてきますよ、ということが言いたかったのです。
今、なかなか出かけられなかったりすると思います。そんな時間に曲作りなんてやってみるのもどうでしょう。
Lineアカウントからブログ更新をお知らせ!
がっきや速報
人気blogランキングへ ![]()
![]()